他学会・講演会等の開催情報
このページに学会・講演会等の情報の掲載を希望される場合には、以下の連絡先まで、リンク先やその他の必要な情報をお寄せください。もし可能でしたら、こちらのテンプレートの通りにお願いいたします(作成が難しい場合は通常のフォーマットのもので構いません)。なお、エイチティーティーピーから始まるリンクに関しては、安全ではないと判定される可能性が高いため、エイチティーティーピーを★に置き換えて掲載させていただきます。また、会員メーリングリストによる周知をご希望の場合はあわせてお知らせください。その場合、メーリングリストで周知する文面をメールタイトルも含め、別ファイルでご用意ください。
連絡先: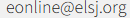 [お手数ですが、手入力をお願いいたします。]
[お手数ですが、手入力をお願いいたします。]
※送信後、休日を除き72時間以内に掲載されない場合には、事務局に届いていない可能性があります。再送信いただくか、事務局にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
学会・シンポジウム・講演会
東大英文学会および後藤和彦先生最終講義
【日時】2026年 3月14日(土)15:00-17:30
【場所】東京大学本郷キャンパス 法文2号館1番大教室
【概要】
古屋耕平「文系とAI——アメリカ文学の場合」
後藤和彦(最終講義)「Mark Twainと夏目漱石——追憶と諧謔」
【参加方法】参加自由・無料
【懇親会】
同日 18:00-20:00
会場:カポ・ペリカーノ
会費:10,000円(学生5,000円)程度の予定
登録フォーム: 東大英文学会総会 2025-26 - Google Forms
ご回答期限: 2026年3月1日(日)
【お問い合わせ先】eng☆l.u-tokyo.ac.jp(☆をアットマークに)
日本ホプキンズ協会例会
[日時] 2026年2月22日(日)13:30~17:00
(Zoomによるオンライン開催)
【概要】ジェラード・マンリー・ホプキンズの詩の試訳と解説を担当者が行い、そのあと、その発表内容について詳細に検討します。テキストはW. H. Gardner and N. H. Mackenzie, eds., The Poems of Gerard Manley Hopkins, 4th ed., Oxford Univ. Pressを使用します。
【参加方法】参加ご希望の方は、お名前とご所属をお示しの上、2月17日(火)までに下記問い合わせ先までにご連絡ください。
【プログラム】
13:30~17:00 (途中20分の休憩)
Lines for a Picture of St. Dorothea-Dorothea and Theophilus (25) stanza 7
担当 桂山 康司
Rosa Mystica(27)stanzas 1-4
担当 高橋 美帆
【問い合わせ先】日本ホプキンズ協会事務局 高橋 美帆
miho☆kansai-u.ac.jp[お手数ですが、☆をアットマークに変更の上、手入力をお願いします]
詳細は学会のHPをご覧ください。
日本国際教養学会(JAILA)第14回全国大会
【日時】2026年3月14日(土) 9:15~ ※ 受付開始は8:45
【場所】宮城教育大学[2号館3階]仙台市青葉区荒巻字青葉149
【概要】
日本国際教養学会(JAILA)は、研究分野の細分化と専門化が果てしなく続く現在の研究および学会活動の潮流の中で、真に必要とされる知識と教養を国際的な視野に立って共有することを目的とし、哲学、歴史、社会科学、自然科学、芸術、教育、外国語、環境など多方面にわたる研究活動を行っております。全国大会も14回目を迎えました。
大会の詳細につきましては、JAILAホームページをご覧ください。「大会案内ページへのリンク」から、口頭発表プログラムと発表概要集(現在準備中)、その他詳細のご案内をご覧いただけます。
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
【参加方法】
対面形式(ポスター発表、特別講演はオンライン参加可)
参加申込フォームで受け付けております。
対面参加、オンライン参加ともに事前のお申込みが必要です。
[申込締切]3月4日(水)正午
【プログラム】
詳細はJAILAホームページ上の「大会案内ページへのリンク」へ。
以下、特別講演のご案内です。
15:20〜16:50
【司会】Dr. Nami Sakamoto Doshisha University
【講師】Dr. Sender Dovchin Curtin University
【演題】First Languaging and First Knowledging and the Future of Indigenous Education: Perspectives from Australia, Mongolia, and Japan
【内容】
First Nations peoples have sustained their cultural and linguistic practices for tens of thousands of years, developing sophisticated First knowledge of nature, land, water, sky, seasons, astronomy and navigation since the earliest moments of human existence. Although they may not have relied on modern technological instruments, they have long possessed intricate knowledge systems that continue to sustain their languages, cultures, communities, and ecosystems across generations. This profound practice of First Knowledging also brings forth an awareness of First Languaging - the living and evolving expressions of First Languages that have existed since the dawn of humanity. Humans have always been languaging; yet First Nations peoples have preserved a unique clarity and connection to this essence. For them, language is not merely a means of communication but an interwoven tapestry of spiritual expression, storytelling, and embodied systems of First Knowledges that nurture both cultural and ecological worlds.
This lecture explores the intersections of First Knowledging and First Languaging among Indigenous communities in Australia and Mongolia, illuminating how linguistic and cultural continuity shape identity, learning, and belonging. By examining the dynamic interplay between Indigenous and dominant languages across homes, schools, and communities, it identifies pathways for embedding these epistemologies in curriculum design and classroom practice. Extending to Indigenous contexts in Japan, the lecture considers how First Languaging and First Knowledging can inform transformative, inclusive, and culturally responsive approaches to Indigenous education for the future.
Lecturer Profiles:
Professor Sender Dovchin is Dean International, Faculty of Humanities, and Senior Principal Research Fellow at the School of Education, Curtin University, Australia. She is an internationally recognized scholar in applied linguistics, known for her research on translanguaging, migrant and Indigenous education, and language ideologies and identities. She has been named a Top Researcher in Language & Linguistics by The Australian Research Magazine (2021, 2024) and listed among the world’s top 2% most-cited linguists (Stanford University list).
【お問い合わせ先】
JAILA大会運営委 jaila.annualmeeting☆gmail.com(☆をアットマークに)
Tsukuba Morphology Meeting 3 “Beyond Productivity and Word-Formation: Insights from Onomasiological Theory”
【日時】2026年2月19日(木) 13:20 ~ 16:50
【場所】筑波大学つくばキャンパス第一エリア1D棟201教室 (筑波大学第一エリアへのアクセスはこちらをご覧ください)
【概要】「新たな語はどのように生成され、解釈されるか」という問題について、名義論(onomasiological theory)の枠組みを軸にして検討する国際ワークショップを開催します。名議論は、語の形成や解釈も、話し手のコミュニケーション上の意図(「何をどのように伝えたいか」)から出発すると考える点が特徴です。スロバキアを拠点にして活躍している名義論の著名な研究者による講演や発表に、構文形態論、分散形態論を専門とする日本人研究者による発表をおりまぜ、語の意味や生産性、創造性、競合といった言語学の主要概念に関して、フロアの参加者とのやり取りを交えながら、文化論、言語教育などを含めた幅広い観点から議論していきます。多くの研究者、学生のみなさまのご参加をお待ちしております。
【参加方法】対面開催、事前予約不要
【司会】納谷亮平 (筑波大学)
【プログラム】本会の使用言語は英語です。
13:20 – 13:30 Introduction
13:30 – 14:25 Lívia Körtvélyessy (Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia) “On the Interplay of Productivity, Creativity, and Structural Richness”
14:30 – 15:00 Pavol Štekauer (Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia) “Competition between Word-Formation Strategies in View of Meaning Predictability”
15:00 – 15:15 Break
15:15 – 15:45 古賀健太郎 (青山学院大学) “A Constructionist Approach to the Formation of Phrasal Names in French”
15:50 – 16:20 田川拓海 (筑波大学) “Japanese Denominal Verbs in Digital Game Discourse”
16:20 – 16:50 Discussion
【共催】筑波大学人文社会系
【お問い合わせ先】長野 明子 nagano.9☆u-shizuoka-ken.ac.jp(☆をアットマークに)
越境するナラティブ―他/多言語による文学は何を紡ぐか―
【日時】2026年2月14日(土) 13時00分~17時00分
【場所】富山大学人文学部3階第6講義室(富山市五福3190)
【概要】
移民の増加、戦争や迫害による難民問題、グローバル化や多文化共生など、現代社会は一国の枠組みでは捉えきれない課題に直面しています。こうした変化の中で、文学もまた、単一言語による「国民文学」の枠組みを越え、複数の言語や文化のあいだで生み出されるものとして注目されるようになってきました。
本シンポジウムでは、人々の「ナラティブ(語り)」が国境・文化・言語を越えて伝わるとき、何を喪失し、何を継承し、何を生み直してきたのかを検証します。そして、文学という営みを手がかりに、「越境」が不可避な現代社会における他者との共存や、記憶の継承・再構築の問題について考える新たな視座を提示することを目指します。当日は、6名の研究者が、それぞれの専門分野の立場から、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、あるいは特定の地域や国家に収まりきらない人々や集団におけるナラティブのあり方について発表します。発表後には、登壇者によるディスカッションも予定しています。
【参加方法】対面開催、事前予約不要
【プログラム】
13:00–13:10
開会挨拶 秋田 万里子(富山大学)
________________________________________
13:10–13:35
【講師】西 成彦(立命館大学名誉教授:ポーランド文学・比較文学)
【演題】「旅するひと、旅する言葉」
【司会】福島 亮(富山大学)
________________________________________
13:35–14:00
【講師】秋田 万里子(富山大学:ユダヤ系アメリカ文学)
【演題】「消えゆくものに息を吹き込む――『ヒストリー・オブ・ラブ』における 翻訳と継承」
【司会】福島 亮(富山大学)
________________________________________
14:00–14:25
【講師】中里 まき子(岩手大学:現代フランス文学)
【演題】「シュヴァルツ=バルトの小説が伝えるユダヤ人の記憶と黒人の記憶」
【司会】福島 亮(富山大学)
________________________________________
14:35–15:00
【講師】福島 亮(富山大学:フランス語圏文学・思想)
【演題】「環大西洋アフリカ人強制移送(DTS)の記憶――アフロトロープを手が かりに」
【司会】秋田 万里子(富山大学)
________________________________________
15:00–15:25
【講師】水野 真理子(富山大学:日系アメリカ文学)
【演題】「日系アメリカ文学史の再考――こぼれ落ちた文学活動を問い直す」
【司会】秋田 万里子(富山大学)
________________________________________
15:25–15:50
【講師】日比 嘉高(名古屋大学:日本近現代文学・出版文化史)
【演題】「越境する文学は何に支えられていたのか――帝国日本の出版文化から考 える」
【司会】秋田 万里子(富山大学)
________________________________________
16:00–16:50
全体討論・質疑応答 ディスカッサント:武田 昭文(富山大学)
________________________________________
16:50–17:00
閉会挨拶 秋田 万里子(富山大学)
________________________________________
【お問い合わせ先】akita☆hmt.u-toyama.ac.jp(☆をアットマークに)
日本シェリー研究センター第34回大会
【日時】2026年3月14日(土)12時30分受付開始
【場所】帝京大学 霞ヶ関キャンパス(平河町森タワービル9階)
【参加方法】ハイフレックス形式 (対面+オンライン)
【プログラム】
1. 12:40 開会の辞 会長 木谷 厳
2. 12:45~13:15 研究発表
【司会】笠原 順路
【講師】菅谷 菜々美
【演題】ワーズワスの“The Brothers”における「墓碑銘」の両義性
3. 13:30~15:30 シンポージアム
【演題】19世紀後半におけるシェリー受容とヴィクトリア朝の詩学(1850–1890)
【司会/コーディネーター】木谷 厳
【講師】松村 伸一
【演題】「長いロマン主義」の連続と断絶――韻律、フィロロジー、二重詩
【講師】木谷 厳
【演題】ヴィクトリア朝後期におけるシェリーのカノン化にJ. A.シモンズが果たした役割
【講師】関 良子
【演題】19世紀後期のシェリー読み直し、あるいは読みかえ――Poetics & Politics
4. 15:45~16:45 特別講演
【司会】新名 ますみ
【講師】阿部 美春
【演題】メアリ・シェリーの死後肖像は何を語っているのか
5. 16:50 年次総会 昨年度分会計報告・役員改選・その他
詳細は日本シェリー研究センターHPに掲載の大会プログラムをご覧ください。
【お問い合わせ先】日本シェリー研究センター事務局 池田 景子
keiko.ikeda☆setsunan.ac.jp (☆をアットマークに変更)
英語圏児童文学会 東日本支部の春の例会
【日時】2026年2月9日(月曜日)
【場所】大正大学 8号館4階(礼拝ホール) 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
アクセスマップ キャンパスマップ
【参加方法】対面開催
お申し込みはPeatixのイベントページにて承ります。
https://higashinihonshibu-grimm20.peatix.com/
*参加費:会員(学生・学生以外)無料、非会員(学生)無料、非会員(学生以外)1,000円
英語圏児童文学会東日本支部・一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団・大正大学文学部人文学科 共催
第20回国際グリム賞 記念講演会(東京開催)
【プログラム】
14:30 開場
15:00 開会の挨拶
15:10- 講演
「『不思議の国のアリス』を絵で表す――記号間翻訳としてのイラストレーション――」
講師 エマー・オサリバン博士(ドイツ・ロイファナ大学リューネブルク教授)
〔講師の紹介〕エマー・オサリバン 博士(Dr. Emer O’Sullivan) アイルランド出身。1980年、アイルランド国立大学ダブリン校でドイツ語、英語、スペイン語の学士号を取得後、ベルリン自由大学でドイツ語と英語の修士号(1984年)、博士号(1987年)を取得。1990年~2004年までフランクフルト大学児童文学研究所で比較文学の教鞭をとり、比較文学や翻訳研究、イメージ論、外国語学習、教育などの分野の児童文学研究において、重要な理論や研究分野を導入し、ドイツ語および英語を使って独創的な研究を発表し続け、世界的な影響力を持っている。2004年からドイツ・ロイファナ大学リューネブルク英文学部教授となる。15冊の著書(編著を含む)があり、150以上の論文がある。2003~2005年には国際児童文学学会副会長を務めた。
〔講演の概要〕 ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』は1865年の出版以来、ジョン・テニエルからサルバドール・ダリ、レベッカ・ドートレメールにいたるまで、無数の画家が絵によって作品を解釈してきました。本講演では、キャロルが言語で表したナンセンスを、画家が図像という記号でどのように再現しているかを考えます。
*講演は英語で行われます。(通訳なし、日本語の概要を配布予定)
16:20 講演終了後、質疑応答
17:00 終了
年度末のお忙しい時期と存じますが、この貴重な機会にぜひご参加いただけますよう、よろしくお願いします。
また、ご担当の学生やご関心をお持ちの方に広くお知らせいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
*大阪国際児童文学振興財団主催の国際グリム賞贈呈式・記念講演会(2月7日大阪開催)はこちらをご覧ください。
英語圏児童文学会 東日本支部 https://jpenjido.jimdofree.com/
【Call for Papers】ELLAK 2026 International Conference The End: Reclaiming the Beginning
Dates: December 17–19, 2026
Venue: Sungkyunkwan University, Seoul, South Korea
Host: The English Language and Literature Association of Korea (ELLAK)
Keynote Speakers
・Jongsook Lee (Professor Emerita of English, Seoul National University; Scholar of Early Modern English and Greco-Roman Cultural Studies)
・Ursula K. Heise (Professor of English, UCLA; Scholar of Environmental Humanities)
・Sean D. Kelly (Professor of Philosophy, Harvard University; Scholar of Phenomenology)
Important Dates
• Abstract submission deadline: February 8, 2026
• Notification of acceptance: March 31, 2026
• Submission deadline for conference proceedings: June 30, 2026
詳細は、こちらをご覧ください。