課題テクスト:Current Issues and Topics (Peter Duppenthaler著、大阪教育図書2008年 1,600円)より、Unit 9 “Gated Communities”
進行役:川崎明子(駒澤大学)、迫桂(慶應義塾大学)
参加者:垂井泰子(秀明大学)、下村美佳(埼玉学園大学非常勤講師)、久世恭子(早稲田大学等非常勤講師)、高橋和子(東京大学大学院生)、佐藤和哉(日本女子大学)、谷本佳子(青山学院大学大学院生・神奈川大学非常勤講師)
■全体概要■
ワークショップ前半では、6名が課題テクストを用いた授業案の発表を行った。それぞれの授業案は、各教員のティーチング・スタイルや英語教育観だけでなく、担当する学生や教育環境の特色を反映した内容であった。後半はグループ全体でディスカッションを行った。日頃抱える悩みや疑問、問題について、時間が不足するほど活発な意見交換がなされた。他の参加者の実践例から多くを学ぶことができ、授業内容と運営を向上するうえで大変有意義なワークショップであった。
各発表内容と全体ディスカッションの概要は以下の通り。各発表のハンドアウトは こちら。(PDF)
こちら。(PDF)
■発表1:垂井泰子(秀明大学)
発表概要:課題テクストを土台として、読解から作文・プレゼンに発展する全4回の授業案の提示。
発表後の質問・コメント・議論内容:
作文の課題について、150語というのは英検で準一級に相当するレベルなので、ある程度の英語力のある学生でないと難しいかもしれない。
作文の課題を行うためには、基本的なパラグラフ・ライティングの授業が事前に必要と思われる。
Wk3で学生が作業をしている間、講師は何をしているのか。
学生の全訳はどのように採点、フィードバックを返すのか。
作文の提出締め切りが、パワーポイントを作成する授業の前日に設定されているが、授業内容の順番を調整すれば時間的にゆとりができるのではないか。
■発表2:下村美佳(埼玉学園大学非常勤講師)
発表概要:一般教養として開講されている英語科目において、英語力と教養の両方を身に
つけることに重点をおいた授業案の提示。
発表後の質問・コメント・議論内容:
各学生が意見を言語化し発表するというのはとてもいい案だと思うが、それは日本語で行うのか、英語で行うのか。
英語科目という枠の中で、内容を深く学ぶ、教えることの難しさについて。
■発表3:久世恭子(早稲田大学非常勤講師)
発表概要: 課題テクストのみを用いた授業と、別の副教材も学習する授業、二つの案の提示。
発表後の質問・コメント・議論内容:
副教材使用について、教科書代が学生の負担にならないか。
内容の深さや、教科書代を考慮した教科書選びについて。
■発表4:高橋和子(東京大学大学院生)
発表概要: 4技能すべてをバランスよく使用する授業案の提示、さらに教員の工夫が必要な点の指摘。
発表後の質問・コメント・議論内容:
課題テクストの最後には語彙定着のための選択問題が挙げられているが、例文が本文内容と無関係である。これとも関連して、教科書に付属の問題をいかに授業で利用するか。(例:設問の順番を本文の要点の内容に沿って変更する)
■発表5:迫桂(慶應義塾大学)
発表概要:英語で行うコンテンツ・ベースの授業案の提示。
発表後の質問・コメント・議論内容:
能力別クラスを想定しているのかどうか。
授業案では、英語についての解説などが一切ないので、文法や語彙力が高い学生が対象でなければ、難しいかもしれない。
■発表6:川崎明子(駒澤大学)
発表概要:基本的な文法事項を定着させ、パラグラフ構成や修辞法を意識して要点を理解し、それに対する自分の意見を論理的に記述させるところまで展開する授業案の提示。
発表後の質問・コメント・議論内容:
文章の解説はどれくらい時間をかけて行うのか。
訳も行うのか。
■グループ全体ディスカッション内容
音読のメリットについて(文法知識があり文章の構造が理解できていなければ、うまく音読ができない。二つの能力は深く関係している)
教科書の選択で考慮すること(例:価格、内容の充実度)。
グループ分けの方法について(トランプ、あみだくじ、学生による自由選択、等)。
総括的なコミュニケーション・スキルといわゆる「英会話」の違いについて。
一般英語科目の目的として、実用性だけでなく教養を追究する場合、内容をいかに深めるか。
文法事項学習の重要性について。
訳読のメリットとデメリットについて。
予習を求めるかどうか。
英語を授業でどのくらい用いるのか。
学生の専攻を授業にいかに反映させるか。(例:授業の中心は学生の専門に関連のある内容を扱い、最後の10分だけ自分の専門に関連する内容を扱う)
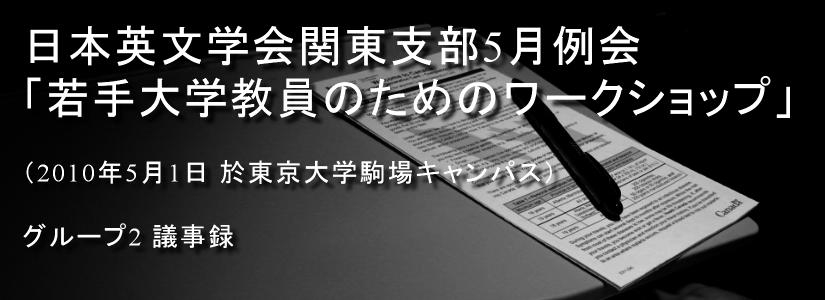
 HOME
HOME 5_1Gijiroku_1
5_1Gijiroku_1